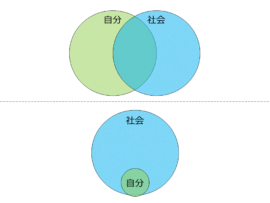地域や社会に目を向けるよりもまず自分を満たすべきかもしれない
カテゴリ:自分事 2017/12/06
自分を満たすために周囲を頼らない
僕自身もできているわけではないということは置いておいて。
やりたいことがわからない、と言うとき、その人は自分自身のどんなニーズを満足させれば良いのかがわかっていない、ということなのだと思う。一方、「地域のために〇〇をしたい」と言うときもまた、その源(ソース)となる自分自身が持っているニーズを考慮していないと感じられるケースが散見される。
もっと踏み込んで言いたいこともある。「人の気持ちや価値観を変えたい」と言うとき、大抵の場合そう言う本人からは「自分の正しさを示したい」という以上の動機を感じられない。そして、さらには、仮に正しさが示されたことで、その本人が満たされるのかと言えば、どうも本人の満たされるべきものと正しさを示すことでの承認欲求と本人がやることの間の接続がかみ合ってない、ということも。
逆のケースにも言及しよう。
「金儲けしたいんすよね」と言っている人が、儲かりそうな事業をばんばん手掛けてその通りやっているというとき、共感できるかどうかは置いておいて、やっていることと言っていることのずれはほとんど感じられない。健全だし、気持ち良い。むしろ、自分が儲けられるということを脇に置いて「地域のために」とか「win-win」とか言っちゃう方がうさんくさい。儲けたいなら儲けたいでいいじゃない、と思う。モテたい、でもいい。
自分のニーズに素直であり、そのニーズを満たすように動く。それが健康的な循環を生む。自分の欲することを満たすことができなければ、それを満たすことを周囲に依存することになる。だから、外に目が向いて、「地域社会に貢献したい」なんて言葉になる。貢献すること自体が悪いんじゃなくて、他の誰かのために貢献し、他の誰かによって自分を満たそうとするのがあんまり良くないんじゃないの、という話。「やらない善よりやる偽善」と言うけど、その”偽善”を自己満足・自己完結と捉えるならば、周囲を変に巻き込まない分、健全な匂いがする。
自分がエネルギーを発揮したいなら、まずはその受け手を見つけるべきなのだと思う。それを安易に他の誰かに設定すると、往々にしてエネルギーをうまく受け止めてもらえない事態が起こる(受け止めてもらえるように調整していないから)。結果、エネルギーは滞り、淀む。自分のエネルギーの戻り先として自分自身を設定すれば、エネルギーはシンプルに循環する。
ここまで書いて、西村さんが「仕事に人生をかけない」という話を紹介していたのを思い出した。それに近いような、遠いような。この点はまだ咀嚼できていない。
でも、エゴはダメでしょう? という反論への反論
そうは言っても、利己的になったら良くないでしょう? という人がいる。自分だけの利益のために他人に不利益を被らせるのは良くない、と。
そりゃあ、もちろん、良くない。しかし、その意味での”利己的”な振る舞いをする人は、単に自分を満たせていないのだと思う。だから、他人に迷惑をかけても自己利益の追求を止められない。自分がいつまでたっても満たされないから。
この文章を書きながら、僕の脳裏には「地域活性化あるある」な勘違い人種のことが浮かんでいる。「地域を良くしたい!」と言いながら、上から目線で「ああしたほうがいい、これはダメだ」と好き勝手な物言いをし、だんだんと地域の人も取り合わなくなると、「こんなに地域のことを思って頑張っているのに、なんでわかってくれないんだ!」と逆切れするという迷惑な人たち。僕の目には、この人種は先の”利己的”に振る舞う人と同類に見えている。
ちょうど、この本のP.190にも「利己」と「利他」に関する言及があった。幸福学では「利他」が幸せの極致ではあるが、そもそも「利己」と「利他」は意識(ego)を手放せば区別できるものではなくなるよね、という話。
「利己」と「利他」を区別するから、”「利己」は良くない―「利他」は良い”という二項対立になる。この構造から離れて考えるべきなのだと思う。
自分-社会の捉え方を変えてみる
僕が海士町にいたころ、生徒の将来の夢ややりたいことを一緒に考えるというときに、良くこの図の上側を用いて説明していた。「自分のやりたいことと社会が求めることの重なりの部分を模索しよう」と。
ところが、最近になって面白い話を聞いた。そもそも、自分だって、社会の一員だよね、と。ベン図を分けて描くことが多いけど、実は自分だって社会に内包されているよね、と。
この話は僕の中で強く印象に残っており、この記事を書く動機にもなっている。そうであるならば、自分自身を満たそうとすることが、すなわち、社会のニーズを満たすことであろう、と。
逆に、「利己」と「利他」を区別し、「利他」に走ろうとすれば、誰をも満たさない事業やサービスが生まれる。生まれるというか、誰も(本人すらも)求めていないので立ち上がらずに終わる、または早々に撤退する、という結末になるのだろうけど。
「地域SNS」なんていい例で、確かにそれが機能すれば地域内/地域間のコミュニケーションが促進され、キープレイヤーがつながり、よりインパクトが大きくなりそうというのはロジカルに想像できる。しかし、機能させるところに、人間社会のリアリティが立ちはだかる。利己/利他の区別は、このリアリティを見落とさせる働きがあるように感じられる。
こういうときに思い浮かべるのが「黒いお皿」の話だ。新商品開発に乗り出した食器メーカーが、主婦10数人を集めて、これまでにないお皿をつくるとしたらどんなものが欲しいか、というインタビューを実施した。そこで出た意見が「黒いお皿」だった。確かに、黒々とした食器と言うのは「これまでにない」。インタビューの主婦たちは「珍しいよね」「欲しいよね」と乗り気だった。しかし、実際に販売したところ、まったく売れなかったという。
どうやったら自分を満たせるのかを自覚している人は、実は少ない。他人の「あったらいいよね」は意外と信用ならない。「利己」はダメだけど、「利他」だけでもダメなのだ、たぶん。
それでも他者のニーズを満たす手段としてのデザイン思考
先ほどの図の下部に視線を戻そう。この図は、自分のニーズを満たすことが、社会の他の誰かのニーズを満たすことにつながる、ということを表している。それは利己/利他の区別を超えた次元の話なのだった。
では、自分でない他の誰かのニーズを満たすことは可能なのか?
雑な議論になるが、そのための手段の一つがデザイン思考なのではないかと思っている。徹底的に他者の視線を獲得しようとする試み。素早くプロトタイプを繰り返し、頭の中の仮説を厳として存在する現実に向けて漸近的に近づけようとするプロセス。自分でない誰かのニーズをその本人以上に共感的に理解していくことによって、自分でない誰かのためのプロダクトを生み出す。
すでにあるニーズに対してさらに良いプロダクトで応える持続的なイノベーションは、絶滅はしないものの、既存のサービスで衣食住が十分に満たされている時代においてはどこかで限界にぶつかる。そういう意味でも、世界中の企業がデザイン思考に着目しているのは、当然のことなのかもしれない。
(こう書いていて気づいたのだが、自分のニーズに接近するにも、他人のニーズに接近するにも、結局他者の手が必要、と言えるのかもしれない。が、この議論については本文末尾で言及する)
自分を取り巻く言語の限界に挑む
ニーズを満たす、と簡単に書いたが、デザイン思考といった手法が”わざわざ”発明されたことからもわかるように、事はそう単純ではなかった。恐らく、その難しさは、僕たちが心の奥底でぼんやりと感じていること、無意識に抱いている前提や価値観が、日常の中で使われる”言語”で表現されがたいものとしてあることに起因するのかもしれない(普段の言葉で表現できるならば、それは意識化を免れない)。
ある人から拝借したこの本の3章で、南方熊楠が何に挑んでいたのかが考察されている。僕自身、ほとんど咀嚼できていないのだが、ここに何かしらの糸口があるように感じている。
紹介されていたのが、ラカンの「現実界」「想像界」「象徴界」という分類だ。
・現実界・・・人間の心の働きの外部にあるもの。「自然」。
・想像界・・・人間的な心を形成するもの。イメージによる思考。
・象徴界・・・想像界を一旦壊し、記号的な言葉の力を借りて主体を再構成したもの。「言語」。
この3者がそれぞれ輪としてお互いに絡み合うことでバランスを保っているとしたとき、どこか1つの輪がゆるめば、他の2者もつながりを保てずばらばらになってしまう、ということらしい。その具体例として、熊楠が頻繁に遭遇した「身体から頭部が離れる体験」が記述されている。
象徴界は言語の働きと密接に結びついていますが、その言語の活動の場所は大脳言語野です。したがって象徴界は頭部に宿っているという身体イメージが、ごく自然なものです。その頭部が身体から分離して、外からや上から身体を見下ろす体験をするのですから、あきらかに象徴界の組み込みに関わる「精神変態」と見ることができます。身体の全体的なイメージをつくりだしているのは、想像界という心のレジスターです。この想像界と象徴界の結びつきが弱まり、それが身体という現実界との分離を引き起こしています。
この話題を厳密に取り扱うには力不足に過ぎるが、熊楠の直面したこの分離は、象徴界=一般に流通する言語によって現実界や想像界を記述しきることができないという事態によって引き起こされたのだった。具体的には、熊楠は彼の業績として広く知られる「粘菌」の研究において、この分離に立ち向かわなければならなかった。というより、この本に従えば、否応なく直面するこの分離の意味するところと対峙し、現実界や想像界に真に対応する象徴界=言語を構築するプロセスとして「粘菌」の研究に着手した、という方が正しいのかもしれない。
結局何が言いたかったというと。
僕らは僕ら自身の言語の範囲に応じて、現実を記述することができる。逆に言えば、言語の記述できる範囲を超えて現実を把握することはできないということだ。実際、目の前に起こる現実がもたらす情報は、無意識の取捨選択によって認知されるに至るという(逆に自閉症スペクトラムの当事者の中には、取捨選択がなされないため、健常者が無視する余計な情報もすべて受け取り、情報過多になるという例もある)。先述した通り、無意識に抱くもの、ぼんやりとしたイメージは、言語化できないから「無意識」であり「ぼんやりと」しているのだ。
こうした見方に立つと、自分が満たされたいニーズを把握することは、自分が持っている言語の限界への挑戦でもある。また、その挑戦は終わりを知らないし、漸近的な接近でしかないのだろう。先に紹介した「無意識と「対話」する方法 – あなたと世界の難問を解決に導く「ダイアローグ」のすごい力 – (ワニプラス)」では、「古層へ潜る」という表現がなされていたが、勝手に近しいものと捉えている。
言語の揺らぎと社会構成主義
では、いかに象徴界=言語を、現実界や想像界にフィットさせることができるのか。”言語”を狭義に捉えるならば、「英語やスペイン語を学べばいいってこと?」となる。確かに、それぞれの言語には何らかの前提があるはずで、それを学ぶことで世の中の見方が変わるということはありえるかもしれない。もう少し広義にとらえるならば、恐らく「社会構造主義」が有効になるのではないか。少し長い引用をしてみる。
マーティンは、教室や実験室で使用される生物学のテキストの中で、女性の身体がどのように記述されているかを分析しました。分析の結果、マーティンは、女性の身体が、子孫を残すことを第一の目的とする一種の「工場」として表現されているという結論に達しました。そして、月経や更年期は、「生産性がない」ため、無駄な時期であるかのように扱われていると考えました。一般的な生物学の教科書の中で、月経について記述するために用いられている用語を、ここに書き出してみることにしましょう(強調はガーゲンによる)。
「プロゲステロン(黄体ホルモン)とエストロゲンが減少し、非常に分厚くなった子宮内膜を維持していたホルモンの働きが損なわれる」、血管の「収縮」によって「酸素や栄養物の供給が減少する」、そして「内膜が維持できなくなり、内膜全体がはがれ落ち、月経が起こる」、「ホルモン刺激が欠如した結果、子宮内膜の細胞は壊死する」。別のある教科書では、月経を「子宮が赤ちゃん不在のために泣いている」ようなものだと表現しています。
著者は、生物学という自然科学のテキストにおいてもある種のイデオロギーが含まれており、必ずしも中立とは限らない表現がなされている場合があること、また、ここが重要なのだが、それはまた別様に特徴づけることも可能という点を、社会構成主義の視点から指摘している。
僕らが当たり前に使う言語には、すでに何らかの前提やイデオロギーが組み込まれている。それによって、同じ”現実”を見たはずの人たちが結果として異なる解釈に至るということも珍しくない(「群盲象を評す」等)。「粘菌」という、これまでの言語に矛盾を突きつけうる「自然」(=現実)を手がかりに熊楠が挑んだのは、西洋流の自然科学が孕む限界(=ロゴスの法則に従い、因果関係で記述する作法)だった。
象徴界=言語の側から自然や漠然としたイメージをとらえようとすると、それはいつまでたっても一様な姿しか見せてくれない。しかし、現実界や想像界の方に目を向けてみることではじめて、これまで用いてきた言語の不自由さに気づくことになる。この試行は3者のバランスを揺るがすリスクに直結するが、この揺らぎを乗り越え象徴界の新たな形式をもたらそうとするチャレンジによって、言語が拡張される(あるいはこれまでと異なる構造を持った言語に出会う)ということになる。そうしたチャレンジの先にあるのが優れた芸術(アート)であり、熊楠が見出そうとした新たな学問の地平であった。
終わりに―方法としてのダイアローグ
途中から思いがけず抽象的な飛躍を遂げてしまったが、最後にまとめに取り掛かってみる。
この記事で取り扱ったのは、「まずは自分を満たそうよ」という提案である。前半では概念的な説明を、デザイン思考以降ではその手がかりとしての様々な理論や方法をそれぞれ提供したつもりだった。
「自分を知る」というのは容易なことではない。僕の周りを見ても、深く自分を理解しているなと感じる人ほど、日々様々な視点を得ようとしているように見受けられる。ただ一つの正解に達するということはもしかしたらあり得ないのではないか、というのが、現時点での僕自身の前提になっている。
多様な見方を獲得するための単純な方法は、他人の見方を知る、ということにある。それはモノローグ(独り語り)ではなしえないことかもしれない。僕自身が先ほどの前提に立って探究しているのが、ダイアローグという方法だった。
自分自身の言語=象徴界が唯一であるという姿勢を一瞬でも崩すことができなければ、他者とのコミュニケーション(それは読書等をも含むかもしれない)の結末に待つのは同調か対立かの2通りしかない。ダイアローグに求められるのは、自分の用いる言語の範囲では語りえないものがあり、それを語りうる他者がいる(かもしれない)というスタンスにあるように思う。
自分と異なる考え方は「間違い」なのか、それともそれは単なる「違い」なのか。社会構成主義は、「個人主義的な自己」という概念の限界を指摘し、「関係性の中の自己(”私たちは、お互いによって作り上げられている”)」という新たな見方を提示している。モノローグという一方通行のコミュニケーションにとって代わる関係の在り方―「対話」の可能性が、ここでも強調されている。言うことよりも聞くこと、結論付けることよりも問うことの意義がここに詰まっているように思う。
自分がこれまで当たり前だと思っていたことが揺らぐその瞬間が、対話の糸口なのだと思う。その綻びを新たに紡ぎなおす言葉は、何も自分の力だけで生み出さなければいけないものでもない。
僕は秋田でダイアローグを大切にする場をつくりたい、と”ぼんやりと”思っていた。そして、先月末には、それを体現する機会に恵まれた。そのときの諸々は別の記事にまとめている。本記事は、そのワークショップの前後でそれこそ多様な他者(年上もいれば年下もいれば過去の偉人もいる)から学んだことの一つの結実として書かれたものだ。
僕自身、自分自身をどう満たせばいいのか、検討がついていない。しかし、この秋田に戻ってきてから、五城目という自由なフィールドで、少なくとも「自分が満たされないことはしない」という働き方を1年ちょっと続けてみたことで、ゆるやかにではあるもののその方向性が見えてきている。それは自分一人では気づけなかったことだし、自分が考えていることを実行し、そのフィードバックから学ぶという繰り返しの産物であるように思う。誰かの何気ない一言から新たな問いがもたらされる場面も多々あったし、ここまで付き合ってくれた人ならわかる通り、多くの本の影響を受けている。
なぜ、ダイアローグなのか。ダイアローグとは、何か。うまくまとめきれないが、こんな感じだろうか。
可変性のある自分として他者と関わる中で、自分自身の前提や価値観の存在に気づき、目の前で起きている生々しい現実やもやもやと抱えている無意識のイメージに接近するための新たな問いに出会うための方法
まだまだ「自由研究」は終わらなさそうだ。