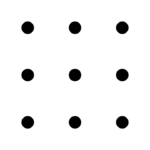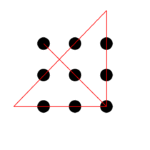カテゴリ:自分事
2017/02/09
「変化の原理」を読んで印象に残っていたのが「相手の『言語』を話す」という表現だった。ブリーフセラピーの現場では、治療者はクライアントに具体的な指示を出す。しかし、その指示通りに動いてくれるかどうかは、そのクライアントに合わせて指示を出せるかどうかがポイントとなる。
教員が、学級崩壊の如く騒然とした教室で「先生の言うことを聞きなさい!」と大声で指示したところで、子どもたちがその指示に従わなさそうであることは想像に難くない。相手に指示をするということは、そのまま相手が指示通りに動くという結果を生み出すわけではもちろんない。
相手の「言語」を話すということ
相手の「言語」を話すということは、「話し手がどんなふうに世界を見ているのか丸ごと感じ理解しようとする」ためのアプローチの一つだと思う。「話し手を観察する」のではなく、「話し手の目から見える世界を見る」という試み。相手が意識するしないにかかわらず用いる言葉を大切に扱い、相手の話をそのままに受け取り、それを損なわなずに話す、という言い方がよいのかもしれない。
センスもあるのかもしれないが、自らの感受性を、相手の「言語」をきき、きき手の側もそれを用いるということに集中させるという意味では、かなり意識的な働きが強いのだろうと思う。僕自身、インタビューを幾つか実践してみると、出来不出来は置いておいても、そうして意識的にきこうとすれば、驚くほど消耗が激しいことを自覚する。
その意義
どうしてそんなことをわざわざしようとしているのか、を改めて考えてみた。僕が考えているメリットは例えば以下のようなものになる。
・話し手の「言語」を用いることが話し手の納得、「きき手はちゃんときいてくれている」という安心につながる。
・話し手が自分自身の「言語」を自覚し、これまで疑いもせず振り返ることもなかったこれまでの認識について深く考えるきっかけにつながる。
・話し手の言葉をきき手が理解した「つもり」になってしまうことを避け、謙虚な態度で話し手の言葉に耳を傾けることができるようになる。
これらの観点は「ひとのはなしを遮らず促すようにきく」ことを主要な関心としている。しかし、そこからさらに一歩踏み込んで「話し手の抱えている課題や悩み事を解決する」という段階になっても有効であると思っている。例えば、こんなふうに。
・話し手の文脈に無理のない形で介入(冒頭の言葉を用いるならば「指示」)することができる。
・話し手が「課題を解決できていない」状態を責めるのではなく、むしろそうした状態でありながら自分なりに課題に当たろうとする態度に目を向けることで、敬意をもって対応することができるようになる。
特に相談を受けるようなケースでは、相談をする側の方が立場が下になりやすい。そういうとき、敬意をもってきくことの重要性が増してくる。「どうせこんなことで悩んでるんでしょ」といった具合についついパターン化したくなるところをぐっと抑えないといけない。
その背景・人間観
というようなことを考えていると、なんとなく、ある一つの人間観のようなものが見えてきたのだった。単純に書くと、こうなる。
「ある人にとっては、その本人が最大の当事者である」
例えば「悩み事」にフォーカスしてみると、その最大の当事者であるということは、その「悩み事」について最も多くの情報量を有し、最も長い時間をかけて向き合い、最も試行錯誤(あるいは四苦八苦)している、ということ。その本人を差し置いて誰がその人の「悩み事」を解決できるのだろうか、というスタンス。
これは「解決に至れない本人に問題がある」という自己責任論につながる危うさがあるが、そういうつもりはない。相手の「言語」を用いながらコミュニケーションをとることが、相手は自分の認識をよりクリアに自覚する助けになるかもしれない。そうして真の問題が見えてくることで、本人が自らの力で解決できるかもしれない。この可能性を信じる、というニュアンスを強調したい。
人それぞれ世界をどう見ているのかは異なるという前提に立つことではじめて、きき手が自分の理解や考えを押し付けるのではなく、その当事者の言葉に耳を傾けることの意義に目を向けることができるのだと思う。
関連する記事
カテゴリ:自分事
2017/02/01

「少年自然の家」というものがどれくらい一般的なのかは秋田で子ども時代を過ごした僕にはわからない。自然体験やキャンプ、カヌーといったアクティビティ、あるいは集団生活の実践を通じて青少年を育もうという目的を以て建てられた施設がある。そこは小学校単位での林間学校(その言葉を僕自身は使ったことはないが)の会場として利用されるほか、施設単体で独自のプログラムを企画し、近隣の小中学生を受け入れていた。
僕は小学校4~6年の間に「保呂羽山(ほろわさん)少年自然の家」に12回ほど足を運んだと記憶している。そこのプログラムはほとんどが宿泊を伴うもので、基本的には親は同伴せず子供たちと施設側の大人+ボランティアだけで過ごすことになる。たいていは週末や連休に設定できる1泊2日か2泊3日の日程が多かったように思う。期間中ひたすらにカヌーを練習するものもあれば、キャンプ場近くの山でスキーを楽しんだ翌日に雪山登山に挑戦する、というものまで、季節毎に幅広くかつエキサイティングなメニューがある。当時は、1年に1、2回ほど、たいてい長期休暇の時期を狙い定めて、4泊5日という小学生対象にしては割と長いキャンプが催されており、僕は夏の4泊5日のプログラムに3年連続で参加していた。ちなみに、秋田県が管轄する由緒正しき「教育施設」なので、毎回の参加料は都市部の人なら驚愕するほどの安さであったことも付け加えておく。
なんでこんなことを突然書き始めたのかというと、ある人から聞いた「最近は親も学校もどんどん過保護になってきている」という話をふと思い出したからだ。ある学校では、宿泊を伴う学校行事の日数が1泊分減らされたそうだ。
「子どもだけで3泊もするなんて考えられない。親元から離すのが不安だ。もっと短くしろ」
そんな声があったとかなかったとか。ひどい話だな、と思う。親元を離れた方がかえって子どもたちはのびのびと過ごせるかもしれないのに。あるいは、親がいないところで、自分で考えて、自分で試してみて、失敗したら周りの友達や大人に助けてもらう、そんな機会になるかもしれないのに。もったいない……なんて呑気に構えていたのだけれど、そこで、あ、と声が漏れた。
そうか。過保護な親の目線からは、僕の両親もまた、その非難の矛先に立っていることになるのか。子どもをほぼ毎シーズンのように数日間家の外に出させて、ひょっとしたら子どもの世話から解放されようなんて魂胆なのではないかと、あるいは勘繰られていやしないだろうか。それであるならばこれもまた不本意なことだ。
しかし、一方で、物事を自分の手元から離すこと、手放す、委ねる、あるいは任せるということの難しさも、よくわかる。曲りなりにも約5年半の間、島の公立塾で高校生と接した経験を持ってもなお、「手放す」と「放任する」の違いがよくわからないでいる。ほどよい距離の取り方がいまいちつかめない。ひとたび介入すればついつい手綱を引きたがってしまう。ところが、なるべく距離を取ろうと決心すると今度は転んだタイミングで立ち直るサポートに入れず、結果的に挫折させてしまう(一回転んでやめれることならやめちゃえばいいじゃん、という思いもあるにせよ)。
そして、また、ああ、とため息交じりに上を向く。僕の親はよく手放せたもんだな、と。受験する大学も特に親から指定されることはなかった(東京の私大への進学が決まった後に「もっと手堅い国公立大に行ってくれたら学費も安かったのに」とは言われたけれど)。それでも「参考書が欲しければお金はちゃんと出すから」という声掛けもまたあった(あまり有効に活用できたとは言えないが)。もちろん、「少年自然の家」通いができたのも親の理解とサポートあってこそなのだ。
中学生の頃だったか、こんなことを言われた記憶が残っている。「お前が大学に行きたいと思うなら、そのための学費をねん出する用意はある」と。それまで自分が大学に行くなんて微塵も思っていなかった僕は、その一言で、「ああ、そうか、大学に行くという選択肢があるのか」と思えた。その後、教員という目標を持つに至り、必然的に大学進学を目指すことになるのだが、そこに変な遠慮も後ろめたさもなかった。大学進学という選択肢を一切意識していない小中の同級生や、これまで接してきた高校生を見れば、それがどれだけ目がぐまれたことなのかを自覚せざるを得ない。
しかし、「大学に行け」と言われたわけではない。もしかしたら親にはその期待があったのかもしれないが(田舎には珍しく両親ともに大卒だったし)、もしかしたらそこに秘められていたかもしれない意図を認識する暇もなく東京に出てしまったのだから、それはまさに「子どもに委ねる」という両親の試みが成功裏に終わったという証なのだろう。
「少年自然の家」でのアウトドア体験や、その場所で初めて出会う同年代との共同作業を経て、果たして今の自分に何がどれだけ残っているのかは定かではない。ただ、少なくとも、リピーターになるくらいに僕は保呂羽山での経験に熱中していたのだろうし、振り返ってみても、記憶は飛び飛びなのに、「面白かった」という思い出として保持され続けているのだから、悪いことはないに違いないとは思える。
手放して、委ねて、任せることが、どうしてこんなに難しいのだろう。
「過保護」であることは、一体誰のためなのだろう。
自然と、小学校6年生のときに参加した4泊5日の壮絶なプログラムが思い出される。初日の夜は早速駒ヶ岳でキャンプ。翌日に登頂し、下山後、田沢湖でカヌーを練習する。次の日は丸一日かけてカヌーで雄物川を下り、キャンプ泊。4日目はまたまた丸一日かけて徒歩で保呂羽山を目指す。4年生から参加できることを考えると、いかに過激で過酷かが分かる。というか、「保呂羽山少年自然の家」主催なのに保呂羽山に正味一日もいない計算だ。実にむちゃくちゃなプログラムで、きっと後にも先にもこんな行程はなかっただろうと想像する。
「真夏の炎天下で、小学生たちが、20km以上の行程を、歩く」
こう書くだけで正気の沙汰でないことがわかる。暑さと疲労に倒れ、各チームに一人つく大人に背負われた子もいた。大人だって大変だ。ロジを考えるだけでも頭がパンクしそうになる。人数分のカヌーがどこから来てどこにどうやって運ばれたのかなんて、できれば想像したくない。
しかし、だからこそ、それは最高の体験だった。本当にありがたい、の一言に尽きる。いつも親が運転する車のフロントガラスから見えていた「保呂羽山少年自然の家」の文字を視野にとらえたときの感動と感激、そして安堵は、めちゃくちゃな大人たちがいなければ感じることすらできなかったのだから。
あえて書かなくていいことかもしれないが、「手放す」というのは、「手を抜く」のとは決定的に異なる何かなのだろうと思う。それが「過保護」と言われている親たちに届けば、あるいは救われることすらあるのかもしれない。それは、僕がこの言葉から受ける「力の抜け加減」以上に、「本気」を要求することであるように思えてならない。
願わくば、あの真夏の4泊5日のようなめちゃくちゃな体験を、「委ねて、任せて、手放して」みることで実現されるあの充実した時間を、自分も生み出してみたいものだ。
※追記
確認したところ、平成11年度、つまり僕が中学1年生のときまではほぼ同様の4泊5日が行われていたようである。
http://www.pref.akita.jp/gakusyu/horowa11.htm
関連する記事
カテゴリ:読書の記録
2017/01/31
知人に勧められ、五城目図書室に出向き秋田県立図書館から取り寄せてもらった本書(なぜなら絶版だったから)。なんと再出版されていたので、購入してしまった。ずっと手元に残したくなる良書である。「家族療法」あるいは「短期療法(ブリーフセラピー)」という、伝統的な心理療法とは一線を画する手法の基礎を拓いたものだそう。ここに紹介されたその原理は、非常に明快で論理的であると受け止められた一方、幾つかの事例は「常識的」とも「論理的」とも言えない飛躍を伴ったものになっており、その意味で衝撃だった。
「どのように人間の問題は生起し、ある場合にはいつまでも持続し、ある場合には解決に至るのか」
本書で示される原理の出発点となる問いがこれだ。しかし、いかに変化を起こし、問題を解決させるかを検討した筆者たちは、「持続と変化はその正反対な性格にも拘わらず、同一のものとして考えられる必要がある」と考えるに至る。
「九点連結問題」から見る「変化の原理」
理論的な背景は、「群論」と「論理階型理論」の二つの数学分野における成果を(メタファーとして)用いることで示されているが、その説明にはかなりの分量を要するため、代わりに、本書内でも扱われている「九点連結問題」に触れる。等距離に置かれた9つの点を「4つの直線」で「一筆書き」をする、というものだ。
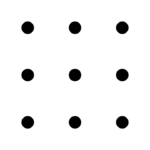
有名な問題なのですぐに解答を示すが、例えば下記のようになる。
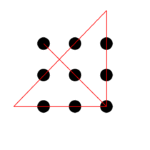
きちんと「4つの直線」で「一筆書き」するという設定にかなっている。「9点の外側に線をはみ出させてはいけない」という(初見の人のほとんどが陥る)勝手な「仮定」を持ってしまうと、一生解くことはできない。つまり、この早とちりな枠組み(ルール)に従っている限り、直線の引き方にいかに変化をつけたところで、「解けない」という状態が維持されるということだ。その逆に、一度そのやり方を覚えてしまえば(ルールをとらえなおせば)、いとも簡単に解答を導くことができる。これが、筆者らが到達した「変化の原理」の端的な例となる。
問題を生み出しているシステムに対し、そのシステムが持つルールに従って変化を起こそうとする限り、そのシステム自体を変えることはできない(同じことのくり返し)。「九点連結問題」の解法が、九つの点に関する「仮定」を検討することで得られ、九つの点自身から得られるのではないように。こう聞くと、かのアインシュタインが残した言葉がふと頭をよぎる。
“The world we have created today as a result of our thinking thus far has problems which cannot be solved by thinking the way we thought when we created them.”
「問題は、それをつくりだしたのと同じ思考で解くことはできない」。本書の内容に則るならば、僕たちは、問題を解決するために、システムの外側に出ることを学ばなければならない。システムのルールに則った内側の変化は「第一次変化」、システムのルールの外側に出るような変化は「第二次変化」とそれぞれ呼ばれている。本書で主に取り扱うのはこの「第二次変化」についてだ。
「問題」、そして「第一次変化」と「第二次変化」
ところで、「第二次変化」の適用対象となりうる「問題」は、そもそもどのようにして”問題化”するのだろうか。
「困難」と我々が言うときには単純に、特別な訓練を必要としないで常識的な水準で解決出来るような事態(普通それは温める対冷やすといった第一次変化のタイプのものにあたる)かもしくは、更によく見られる例でごく日常的な場面で見られる望ましくないが我慢をしてなんとか切り抜けているような日常茶飯事の出来事を意味している。反対に「問題」と言うときには袋小路や行き詰まり、絡み合いといった、初めの困難の対処方法を誤った為に生じた事態を意味することにする。
変化の原理〈改装版〉: 問題の形成と解決 (HUPセレクション)
こでは、シンプルな対応をすればよかったはずの「困難」に対して、誤った「解決」を施してしまったがためにこじれた事態を、「問題」と定義づけられている。「困難」を「問題」にまでこじらせてしまう誤った対応というものは、主に以下の3つに分類される。
A 「極端な問題軽視」・・・行動が必要な時に行動しない誤り(「それは問題ではない」と否定することによって解決を試みる)
B 「ユートピア」・・・とられるべきでないときにある行動がとられる誤り(実際には変えることが不可能かもしくは存在しないような生活上の困難について変化させようと繰り返し努力する)
C 「パラドクス」・・・第一次変化が必要なときに第二次変化を繰り返し試みる、あるいは逆に第二次変化が必要な時に第一次変化を起こす努力を繰り返す誤り(九点連結問題は後者に当たる)
一応付け加えるならば、いずれの「問題」も、当事者たちはある「解決」を何度も試みているという点に注意したい。しかし、そうして繰り返される解決が”誤って”いるために事態はますます悪化し、結果として人間関係の悪化や精神病といった結果を生み出してしまっているという構造がある。多くの場合、先に施される「解決」は「第一次変化」に属するもので、それは「いつも人の常識というものにかなっている」のだが(例えば「群衆の反抗に対してカウンターの反抗をもって」鎮圧を試みる、など)、それこそが「同じことのくり返し」を引き起こしている、というのが著者らの考えだ。
逆に、こじれた「問題」に対する「第二次変化」は、「奇妙で予想外で常識外れのものにみえる」もので、しかもそれは「問題」に対してこれまでなされてきたこと、すなわち「第一次変化から見て解決だと見えるもの」に対して適用される。本書の記述を参考にすると、ある事象aが起きようとするとする。この時、常識的にはそれに反対する方法即ちnot-aでaを抑えようとする。しかしこれがまさに「第一次変化」による「解決」である。即ち、aかnot-aかのいずれかを「選択しなければならない」という錯覚に陥っているということだ。それに対し、「aでもなくnot-aでもないもの」こそが「第二次変化」であるという。(これは「ヘーゲルの弁証法」と「同じ原理」に当たる)。
「第二次変化」の(驚くべき)介入の例
より具体的な理解のために、不眠症患者に対し、本書で説かれる変化の原理に従って治療を施した例を紹介したい。彼は日常的なちょっとした困難として「眠れない」という状態に一時陥った(事象a)が、そのとき彼は「自発的に眠らなければならない」という解決を自身に施した(not-a)。つまり、睡眠という自然で自発的な生理現象を意志の力でコントロールしようとした。これは典型的な「パラドクス」だという。以後、彼がなんとか眠りにつこうと努力すればするほど、そのパラドクスは強化され、いよいよもってますます眠れなくなり、不眠症という形で「問題」化する。「物を考えないで故意に眠ろうとする心的な作業自体が皮肉にも逆説的に眠りを妨げ」ているのである。
従ってこうである。第二次変化による介入の目標は彼が眠ろうとすることを阻止することであって、常識的に考えられるような、彼を眠らせる、ということではないのである。
変変化の原理〈改装版〉: 問題の形成と解決 (HUPセレクション)
具体的には例えばこう指示される。「ベッドに横になりとてつもなく眠くなるまで決して目を閉じないこと」と。つまり、「自発的に眠ろうとする」という解決(not-a)こそが「問題」状況をつくっているのであるから、ここでは「aでもnot-aでもない」変化を起こす必要がある、ということだ。
正直、目から鱗どころか、論理的な説明を持って頭では理解できても、納得が追い付いてこないような印象があったのだが、次のような例に触れると、もう少し腑に落ちるところがあるかもしれない。
たとえば、指導する教官と指導される研修生という二者がいたとする。この教官が研修生の信頼を得ようとするならば、それは「私を信用しなくてはならない」というような言葉では到底実現されないのは容易に想像がつく。「信頼とは命令によって手に入れることも生み出すこともできない自発的な何か」だからだ。筆者はむしろ逆説的な言い方が有効である、と言う。すなわち、「私を完全に信頼するということがないように。また何でもかんでも全てを話してくれなくてもいい」と。これによって教官は、「自身が信用する人物に値しないという程度には信頼できると研修生をして信頼させるし、それで両社の研修上の関係を準備できたことになる」。
あるいは。さらにまた別の例を出すならば、公衆の面前でスピーチすることを極度に不安がる人は、自分が緊張していることを恐れていることがある。そうした場合、緊張を悟られまいとコントロールし隠そうとするあまり、ますます抑えることが難しくなり、緊張は強まっていく。むしろ、スピーチの前にこう述べればよい。「私は極度に神経質で不安で仕方ありません。きっとあがってしまいます」と。これによってもはや隠そうとした緊張は公にされ、もはや隠す必要がなくなってしまう。
上述した「第二次変化」による解決はいずれも本書で紹介されている豊富な事例の一部だが、実際に僕自身もそれと知らず取り入れることのある工夫で、イメージをつかむ手がかりとなっているので、ここに引用してみた。
改めて「第二次変化」の実践に当たって
事例に当たったところで、変化の原理を用いた問題解決の4ステップを引用する。
1 問題を具体的に、明確に定義すること。
2 これまでなされた解決への努力を明らかにする。
3 達成されるべき治療目標の具体的定義。
4 この変化を生み出すための計画の設計とその実行
変化の原理〈改装版〉: 問題の形成と解決 (HUPセレクション)
薄々感じていたことだが、第一のステップなどまさに「アクションラーニング」で重視される点と酷似している。
明白だが、なかなか実践しがたい問題解決の最初のステップは、それがどのような問題であろうと、問題の本質を知ることである。すでに聞いたり経験したりしているがゆえに、我々の多くは、何が問題なのか正確に認識し、理解していると思っている。さらに危険なことに、他の人もその問題について自分と同じように認識し、理解していると信じている。
「偽の問題」に何らかの解決策を施したところで「問題」は解決しない。至極当たり前の話だ。次にはこれまでなされた「解決策」を明らかにする。先に触れたように、「第二次変化」はこれまでの誤った解決策に対して適用するものだからだ。そして、治療目標は具体的に定義されなければならない。もっと幸福になりたい、夫との関係をもっと良くしたい、といった目標はあいまいだ。ではその目標の達成のために何をすればいいのか、と考えようとするときに結局困惑することになる。また、解決に当たっては時間制限も設ける。最後のステップとして、新たに検討された解決策を、来談者(クライアント)が納得をもってきちんと実行されるような形で与えられる必要がある。この第4のステップは本書でもいくつか具体例が示されるが、非常にテクニカルであるという印象を受けている。まさにケースバイケースなのだ。ポイントは、治療者は来談者(クライアント)の「言語」をしゃべる能力を必要とされる、ということにあるらしい。
エンジニアやコンピューター技術者の来談者ならネガティブ・フィードバックからポジティブ・フィードバックへの変化の必要性があるのだと言っても良い。自尊心が低い来談者にはあなたは今、自罰が必要で、それには今いった課題をやるのが良いのだと言える。また東洋思想にかぶれている者には禅の公案を思い出させれば良い。「私は来談者、あなたが私の問題を解いてくれるべきだ」と言わんばかりの者には権威者としての態度で臨み、何の説明もなくその指示をすれば良い。専門家の命令だ! と。
変化の原理〈改装版〉: 問題の形成と解決 (HUPセレクション)
これまでのロジカルな解説に対し、この「変化の原理」を用いたプロセスも(もちろん論理的であるけれども)「コミュニケーション」である、ということを思い出させてくれる感じがした。非常にプラクティカルでありながら、決して機械的な仕事ではない、ということがよくわかる。
個人的なまとめとしては(それでも5,000字に及んだが)これくらいにとどめておきたい。気になった方はぜひ一読をすすめたい。専門書にしては平易に書かれており、それほど苦労なく読めると思う。
感想など
本来であれば本書の冒頭で紹介される「群論」と「論理階型理論」について言及するべきだったが、分量の問題もあり、避けながらのまとめとなった。自分自身の理解は進んだが、優れたメタファーだと思ったので、ぜひ本書を手に取っていただきたいと思う。一応、WEB上に「論理階型理論」とブリーフセラピーを紐づけて説明している記事を見つけたので、リンクも貼っておく。
本書の内容が速やかに実生活に反映できるかというと、当然難しさはある。しかし後半で言及したように、「アクションラーニング」との関連や、弁証法的アウフヘーベンとして「第二次変化」がある、という観点など、これまでの知識とリンクすることが多かったという点で、また一つ学ぶべき方向性が見えたように思う。
特に、「治療者は来談者(クライアント)の『言語』をしゃべる能力を必要とされる」という話。僕自身、インタビューの実践を重ねるごとに「相手の目線で見える世界を見る」という地平に迫ろうと努力しているが、その努力が別の形で肯定されたような気分だ。勝手ながら励みにさせてもらった。
残念ながら絶版になっているらしい本書であるが、以下のような関連書籍があるようで、時間があればそちらにも手を伸ばしてみたいと思う。
また、今回のまとめではほとんど触れなかったものの、本書の中では哲学者ヴィトゲンシュタインについての記述が非常に多い。「
」でも大活躍のヴィトゲンシュタイン、そろそろじわじわと手を出す必要が出てきたように思う(下記リンク先はkindle版)。
関連する記事