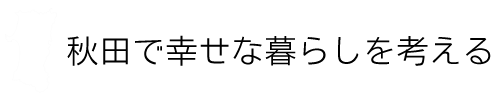カテゴリ:告知
2012/08/01
※2012/08/09追記
おかげさまで「トラ男一家」プロジェクトは目標を達成しました。
ご支援・ご協力ありがとうございました。
トラクター × 男前 = トラ男
農家とあなたがつながる新しいコミュニティ!「トラ男一家」プロジェクト- CAMPFIRE
日本中で農家の後継ぎが年々減少しているというのはみなさんご存知のことと思います。
米どころとして名高い秋田も例外ではなく、米農家すら減る一方。
「きつい」「かっこ悪い」「稼げない」「結婚できない」
家が農家であっても親が子どもに農業を継がせない時代が来ています。
そんな農家の高齢化の著しい秋田の農業に新風を注ぎ込むべく立ち上がったプロジェクトが、「トラ男」なのです。
トラ男×クラウドファウンディング
ソーシャルメディアを活用しながら、生産者と消費者の新しい関係性をつくる。
そんな「トラ男」プロジェクトがクラウドファウンディングサイト「CAMPFIRE」にてパトロン(支援者)を募集しております。
募集期限は8/10 0時まで。それまでに800,000円の資金を集めなければなりません。
農家とあなたがつながる新しいコミュニティ!「トラ男一家」プロジェクト- CAMPFIRE
この記事を書いている8/1現在、183,500円が集まっており、僕を含む25人がパトロンとして名を挙げています。
目標金額まではまだまだパトロンが足りません。
パトロンになれば支援額に応じて秋田の若手農家の手で丹精込めてつくられたお米が届きます。
これがただの寄付とは一味違うところです。
トラ男プロデューサーの武田さんは僕の一つ上の1985年生まれ。
北秋田市(鷹ノ巣)の若手を応援しないわけにはいきませんよね。
みなさま、どうぞよろしくお願いします!
農家とあなたがつながる新しいコミュニティ!「トラ男一家」プロジェクト- CAMPFIRE
↓こちらの本でもトラ男が紹介されています!↓


関連する記事
カテゴリ:告知
2012/06/06
唐突ですが、「Google Lunar X Prize」をご存知でしょうか?
「Google Lunar X Prize」は民間初の月面無人探査の達成を競う賞金レースのこと。
見れば分かるとおり、Google社がスポンサーとなっています。
この「Google Lunar X Prize」に日本から唯一参加しているのが、「White Label Space」。
日本とヨーロッパの合同チームで、あの「はやぶさ」のプロジェクトにも参画した吉田和哉東北大教授が月面探査機の開発リーダーを務めています。
実は、僕の兄が「White Label Space」の広報としてプロボノ的に関わっています。
打ち上げに際しては資金集めが必要ですが、日本国内での認知度はそれほど高くなく、まだまだ課題が残っているとのこと。
「はやぶさ」がもたらしたあの興奮、そして日本人としての誇りをもう一度味わうチャンスが、ここにあります。
ぜひ、みなさまも「White Label Space」へのご協力をお願いします!
ちなみに、現在は月面探査機の愛称を5つまで絞られた最終候補の中から選定中とのこと。
現在、愛称の投票をTwitter上で受け付けています。
月面探査ローバーPM2の愛称最終5候補決定!①ろばくん②Moon Rabit③はくと④月極車輛(つきぎめしゃりょう)⑤なゆた。6月9日24:00投票終了です!文頭に「月面探査ローバーPM2の愛称は」とつけて@まで!詳細→http://t.co/QLNHqnSk AKB総選挙の熱気冷めやらぬ中ではありますが(?)、みなさまの清き一票をよろしくお願いいたします!
※ご紹介したプロジェクトへのお問い合わせはリンク先へお願いいたします。
当ブログではお問い合わせには対応しておりません。
関連する記事
カテゴリ:告知
2012/03/26

秋田魁新報の一面のコラム「北斗星」で海士町が紹介されています。
北斗星(3月25日付)|さきがけonTheWeb
※現在は削除されてしまったようです。
秋田出身ということで、海士町観光協会が運営する「離島キッチン」の佐藤さんと僕も紹介されています。
海士町には、秋田が学ぶべきポイントがいろいろあります。
「ヨソモノ」の受入はその一つ。
とかく「閉鎖的」と揶揄される秋田(県民)。
しかし、これが田舎では至極当然であるということを認めなければ、話は進みません。
それはIターンを積極的に受け入れている海士町であっても当てはまることです。
むしろ、離島という条件下で、海士町は昔ながらのコミュニティをより色濃く残しています。
そんな海士町でIターンが自分の言いたいことだけ言い、田舎の論理を無視する振る舞いを見せたら、たちまち総スカンを食らうことになります。
それでも、海士町には多数のIターンが集まっているのです。
ここに大きなヒントがあるのではないでしょうか。
海士町のIターンである自分が学んだことをきちんと秋田に持ち帰らなければならないと改めて思うのでした。


関連する記事