カテゴリ:自分事
2016/09/09
近況報告的に、いま取り組んでいることについてまとめる。
秋田県の起業家育成支援事業「おこめつ部」

「おこめつ部~農耕型スタートアップ・プロジェクト~」は、想いを起点に社会的インパクトを生み出す事業を、お米を育てるように丁寧に時間をかけて支援します。
おこめつ部~農耕型スタートアップ・プロジェクト~
株式会社ウェブインパクトの一員として、秋田県が主催する起業家育成支援事業の事務局をやっている。秋田に起業の文化を根付かせたいという以上に、特に大学生が、秋田に残り自分の想いを遂げるための選択肢を増やしたい、と個人的には思っている。正直、プログラムが素晴らしすぎて、事務局業務を放棄して参加者側に回りたいくらいだ。詳しくはWEBサイトを見ていただきたい。あと、Facebookページにもぜひいいね!を。
合同会社G-experienceのクリエイティブマーケット事業
五城目には540年続く朝市がある。その朝市に子どもが出店しちゃおう、というのが、合同会社G-experienceのクリエイティブマーケット事業。小学生対象のキッズクリエイティブマーケットと、中高生対象のユースクリエイティブマーケットの2つの入口がある。さらに、中高生向けには、「マイプロ」を深めるオンラインのサポートプログラムを用意する予定で準備中。
今月は9月24日(土)と25日(日)の2日間に渡って実施。初日に出店するものを集まった参加者で考えて準備し、2日目に実際に朝市に出店する。近日中にチラシを作成し、学校等に配布予定。
実は、8月に一度トライアルで実施した。そのときは五城目在住の小学生4名+こども園の子が1名。なんと、商品を考えるはずなのに映画をつくることに。子どもたちの自由な発想には驚かされる。結局、商売にはならなかったものの、子どもたちは「自分たちでも映画を撮れるんだ」という手ごたえを感じてくれた模様。その様子は僕が記事として紹介している。
「自分たちで映画が撮れるなんて思ってもなかった」とその男の子は言った
天狼院書店ライティング・ゼミ
絶賛、文章修行中だ。まぐれ当たりで海士町について書いた記事が10万PVを稼いだらしいが、それ以来鳴かず飛ばず。ホームランを狙うとたちまちフォームが崩れるので、コツコツヒットを積み重ねるつもりで、素朴に記事を書いている。先ほどのキッズクリエイティブマーケットの記事も、文章修行の一環だ。
生前の祖母は、僕が生まれる前に起きたある出来事をきっかけに国内でも稀な難病を患ってしまい、それで僕の記憶の中の彼女はほとんど寝たきりの状態だった。うまく言葉を発することができなかったのも病のためで、祖母と何か会話をしたという覚えがあまりない。
罵倒してしまうくらいに誰かを愛したことがありますか
島根県には、実は有人の離島がある。松江の遥か北、日本海に浮かぶ隠岐諸島がそれだ。その隠岐諸島に位置する海士町(あまちょう)に、僕は5年半ほど住んでいた。そんな僕が言うのもなんだが、この島を訪れるのはあまりオススメしない。きっと、期待を裏切られてしまうからだ。圧倒的に。
島根の離島・海士町にはやっぱり行かない方がいいのかもしれない
関連する記事
カテゴリ:世の中の事
2016/08/15

横手には、老若男女が集まり交わる場所がある。
2016年8月11日・山の日。「あらたな学びのスタイルを考えよう」というテーマの下、横手の「石蔵・MIRAI」に30名近い人が集まった。集合写真を見ていただければ、人口減少県・秋田では珍しく10代後半~20代が多いことがわかると思う。
今回は、横手をはじめとした秋田県出身の学生が仙台や東京から帰省するタイミングに合わせ、県内の社会人や高校生と交流できる機会として企画されたそうだ。さらに、学生が対話的なワークショップに触れる経験を得られるような構成になっており、かつ、ワークショップのアウトプットは主催側が参考意見として今後の展開に活用する、という手の込み様である。
決して一般ウケしないテーマでこれだけの人数が集まるのはなぜか。背景には、主催者の求心力はもちろんのこと、オーガナイザーとしての手抜きのない努力があるのだな、と感じた。
第一部:高校生と大学生の声を聴こう
前半は、高校生と大学生が主役。社会人は耳を傾ける側に立つ。グループに分かれ、学生は自己紹介をしながら、普段の生活のスタイルなどを話していく。社会人は彼らの日々考えていることやニーズを受け止め、把握する。
ディスカッションでもなく、アイデアを深めるのでもなく、まずはシェアをすることから。振り返ってみると、初対面どうしが多いというシチュエーションに適した進め方だったと思う。集まった面々のバックグラウンドのばらばら具合がまた面白い。

自己紹介が一通り終わった後は、主催者側が用意した問いに学生、社会人がそれぞれ回答しながら問いを深める形式。個人的には、特に2つ目の「学生は最初の就職先に何を求めているか」という問いに対する、4人の学生の回答が四者四様で、いろいろ考えさせられた。バランスがほしい、メリハリがほしい、あるいは、次々いろんなことにトライし続けたい……。
自分の中の印象を整理してみると、「リスク」が学生たちの一つのキーワードなのかなと思った。入社してから「思ってたんと違う」となるリスク、(成長できるかもしれないが)厳しい環境に自分が耐えられないかもしれないリスク、入社後に自分のやりたいことが変わってしまうリスク……。様々なリスクを勘案した結果、バランスを求める部分があるのではないか。逆に言えば、現在の学生は世界をそれくらい先が見えないものと捉えている(捉えざるを得なくなっている)のかもしれない。
第二部:新しい学びのスタイルを考えよう
第二部は打って変わってアイデア創発を主体としたワークショップ形式。デザイン思考的エッセンスを加えたシナリオ・プランニングの手法を用いながら、一人ひとりのアイデアを集約して、広げて、深める。最後は2020年という未来の新聞の一面記事という形でグループのアウトプットをまとめた。

内容についてはここでは触れないが、意外にも学生がすんなりワークに入り、自由に自分の意見を表明していた点は素朴にすごいなと思った。割と大学等で経験する機会があるのだろうか。僕がこうしたワークに初めて取り組んだのは、恐らく就職活動のときだった。今の若い世代は、もっと早い。なかなかうかうかしていられないなと思う。
また、僕より年齢が上の方がワークで縦横無尽な言動をしているのも印象的だった。だいたいこうしたワークは年齢を重ねるごとに受け入れがたいものになるものと勝手に思っていた。しかし、少なくともこのMIRAIに集まる方々は違う。積極的にワークに取り組み、学生ともよく交流されていた。
結果的に、10代から60代まで、老若男女が自然な形で交わり協働するよい場になっていたなと思う。それが、この石蔵・MIRAIの本当のすごいところなのだろう。若い人の割合が多めなのも、発言のし易さにつながっていたかもしれない。
まとめと今後に向けて
今回ファシリテーターとして企画・構成と当日の進行を司っていた細谷さんが、「みんなの輪の中に入って一緒にディスカッションしたかったなあ」とぼやいていた。それくらい、相互にアイデアを生み出し合うような良い場だったということだ。今後、ぜひ、参加した学生たちの中で何人かがファシリテーションや場づくりに興味を持ってくれたら、さらに裾野が広がって面白くなりそうだ。そういう贅沢な希望を言いたくなるくらいに、自由闊達な若者たちと触れられてよかったと思う。
関連する記事
カテゴリ:自分事
2016/05/16
![IMG_3174[1]](http://yakimoto.me/wp-content/uploads/IMG_31741-270x203.jpg)
五城目町への引っ越しから約3週間が経つ(転入してからは数日)。
久々の秋田暮らしではあるけれど、車を運転するようになり、
かつほとんどなじみのない土地であるおかげで、
いちいち新鮮に感じられ、騒がしい日々になっている。
上京、都内での引っ越し、海士町への移住。
住むところや環境が変わったことは何度かあったけれど、
毎度これほどに刺激があったものだろうか。
刺激は、活力にもなり、ストレスにもなる。
油断していると、蓄積したストレスをアドレナリンでおさえつけて
変に興奮した状態になっていることがあるようだ。
公道をドライブ中に自覚することもままあり、なお危ない。
もうすぐ30になるというのに、この浮つき具合といったら、
社会生活そのものへの不慣れさではないかと思えるほどだ。
秋田は確かに広く、車の存在は暮らしの経験を一変させる。
さらには、お酒を飲めるかどうかが一日の長さを決める。
秋田の何をも知らず東京へ発った自分を責める手立てがない。
そうして11年が経ち、なるほど多くのことを知ったが、
これからの秋田暮らしではどれも必要なようで決定打がない。
あるとすれば、そうした雑多なものを拾い集めて来た
自分自身の感性だけが、最後に残るもののように思う。
(ということは前の記事にも書いたが)
結局、これからますます問われるのは自分自身であり、
それは「どれだけ蓄積してこれたか」という形としてでなく、
「どれだけ損なわず育めてこれたか」が焦点になるように思う。
僕は、だから、なるべくごまかさず、ぼやかさず、
率直に、自分の感性の導く方へと歩むようにしたい。
今日という日が正解であったかどうかは、
明日という日をどう生きるかによって決まる。
ふとそんな言葉を思いついたのだった。
関連する記事
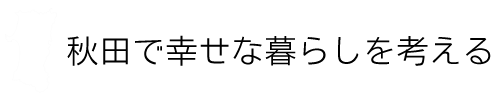




![IMG_3174[1]](http://yakimoto.me/wp-content/uploads/IMG_31741-270x203.jpg)